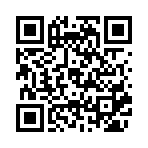2025年01月04日
明けまして2025
初出演とはいえやっぱりスタジオ出演かな、ステージに出るなら2018年のユーミン方式(スタジオ→サプライズでご本人登場!わああバックバンドも豪華!みたいなやつ)かな…とぼんやり予想はしていた。寝かしつけから戻ったら既に終わっていたので、配信で追いかけてぶち上がりました。紅白のB'z、すごかったね!
演出や客席の興奮に胸がいっぱいになるあまり、X(旧ツイッタランド)に語彙力皆無の追っかけ実況を書き散らしてしまった。
大きなエネルギーの塊を受け取ったので、2025年はいい年になるに違いありません。
明けましておめでとうございます!

百貨店のお正月催事で見つけてしまった、福光の老舗のかぶら寿し。かぶもブリも肉厚!
赤子が幼子になり、去年以上に自分の時間がない年末年始。特に予定はないのに、テレビの一挙再放送も大河の総集編も一切観られずに過ぎています。「子が小さいうちはそんなもん」というやつですね。幼少期から年末年始のホームカミングな雰囲気が自分にはマッチしないなと感じていたけど、家族ができてもその感覚が変わっていないことを再確認しています。

アウトドアモールで振る舞いマシュマロをいただいてキャンプ気分。
2024年を振り返ると、家族の職場復帰&保育園入園、5月に突然クリエイターEXPO(クリエポ)出展を決め、五月雨式にモンぬいが襲来…と、未知の扉がパカパカ開きました。客観的には無風だけど自分のなかでは予想外なことばかりだった。まさか自分がぬいぐるみと一緒に静岡を旅する日がくるなんて、人生わかりませんね。

友人たちと三島・沼津・熱海の日帰り旅。メンダコはいなかった。
久しぶりに島に帰れたのも嬉しかったです。また帰りたいよー。海が見たいよー。
仕事面ではクリエポ出展かな。当日以上に、準備…特にパンフレット制作作業が良い経験になりました。需要を鑑みナレーション業務を前面に出すはずが、内なる声を無視できずに音声番組制作を前面に出すことに。結果、これまで経験のあるラジオやPodcastとはまた異なる企画が始まりかけています。導入を検討する企業の要望を伺ったり、実際にデモを試作したりすることができたので、今年はもう少し練って具体的な形にしたいな…。
どんなに世の需要にマッチしていないように見えても求める人はいるかもしれないし、自分の内なる声は無視しない方がいいなと再認識した出来事だった。
クリエイターEXPO出展に関してはnoteにまとめました。合計4本。びっっくりするほど長いけど、よければ暇つぶしにどうぞ…。
第14回クリエイターEXPO初出展の記録_準備編
身の回りのこととしては、友人知人と会う頻度が上がってきた。いい傾向です。知人が東京に来るタイミングで声をかけてもらったり、東京や近郊に住む友人たちと遊んだり。あと、4年ぶりに島に帰ったとき、突然連絡を取ったにも関わらず会ってくれた友人知人たちの「ゆるくばし(もてなし)」の精神が沁みました。島を離れお客さんの立場になって、改めて学ぶことが多い。
SNSやメッセージなどで互いの近況をわかったつもりでも、実際に会って受け取る情報量や空気感はまた別もの。コロナ禍に思い知らされましたが、あらためて痛感した1年でした。人に、会うぞ。
そして健康面。子の風邪をもらう頻度は格段に増えたので気をつけたい。また、日々受け続けるホルモンや気圧の影響を小さく保つための工夫が必要なので、引き続き前向きに対処できたらいいな。
ピラティスもなんとなく続いています。精神性にタッチせず、インナーの筋肉を地味に淡々と動かさ作業性が向いているようです。もう少し頻度を上げられたらいいな…。
さらに、去年の春から送迎用の電動アシスト自転車を手に入れ、車で行くほどじゃないけど距離があるエリアへ出かけるハードルがぐんと下がりました。自転車をこぐ行為も、自分の力で進んでいる実感を伴うのが楽しい。アシストされていても楽しい。行動範囲が広がるとポジティブになれますね。
それらをふまえて2025年。毎年恒例の「漢字1文字を今年のテーマとしてぼんやり掲げる」ですが
「向」
かな。
新しいことや未知の領域へ躊躇いなく向かって行きたい、自分の枠の向こう側にも行ってみたい、自身や身近な人と向き合う時間を取りたい、後ろ向きでも前向きでもアリ、趣向は凝らし続けるぞ…といったイメージです。
これを機に「向」という字について調べてみたところ、家屋北側に設けた明かり取りの窓をかたどっているそうです。実際に住宅をつくる上でも、北向き窓は、大きさや配置の工夫次第で部屋を明るくでき、湿気や風の通り道になるなど、重要な要素の一つらしい。風の通り道…という点では去年の一文字「風」ともリンクしていたので、この漢字にしてみました。果たして。
業務面における長期目標「どんなに細くなってもいいから長く」は今年も継続しつつ、たくさん遊んで仕事して人と会っておしゃべりできたら嬉しいです。
もちろん、お茶やごはんや遊びやお仕事、依頼以前のお問い合わせや雑談などのお声がけも、どしどしお待ちしています。
1人1人が、家族といても、誰かといても、1人でいても、どんな状況や環境のもとにあっても、安らぐ時間があり、心が躍ることを少しでも多く見つけられる、穏やかな1年になりますように。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします!
演出や客席の興奮に胸がいっぱいになるあまり、X(旧ツイッタランド)に語彙力皆無の追っかけ実況を書き散らしてしまった。
大きなエネルギーの塊を受け取ったので、2025年はいい年になるに違いありません。
明けましておめでとうございます!

百貨店のお正月催事で見つけてしまった、福光の老舗のかぶら寿し。かぶもブリも肉厚!
赤子が幼子になり、去年以上に自分の時間がない年末年始。特に予定はないのに、テレビの一挙再放送も大河の総集編も一切観られずに過ぎています。「子が小さいうちはそんなもん」というやつですね。幼少期から年末年始のホームカミングな雰囲気が自分にはマッチしないなと感じていたけど、家族ができてもその感覚が変わっていないことを再確認しています。

アウトドアモールで振る舞いマシュマロをいただいてキャンプ気分。
2024年を振り返ると、家族の職場復帰&保育園入園、5月に突然クリエイターEXPO(クリエポ)出展を決め、五月雨式にモンぬいが襲来…と、未知の扉がパカパカ開きました。客観的には無風だけど自分のなかでは予想外なことばかりだった。まさか自分がぬいぐるみと一緒に静岡を旅する日がくるなんて、人生わかりませんね。

友人たちと三島・沼津・熱海の日帰り旅。メンダコはいなかった。
久しぶりに島に帰れたのも嬉しかったです。また帰りたいよー。海が見たいよー。
仕事面ではクリエポ出展かな。当日以上に、準備…特にパンフレット制作作業が良い経験になりました。需要を鑑みナレーション業務を前面に出すはずが、内なる声を無視できずに音声番組制作を前面に出すことに。結果、これまで経験のあるラジオやPodcastとはまた異なる企画が始まりかけています。導入を検討する企業の要望を伺ったり、実際にデモを試作したりすることができたので、今年はもう少し練って具体的な形にしたいな…。
どんなに世の需要にマッチしていないように見えても求める人はいるかもしれないし、自分の内なる声は無視しない方がいいなと再認識した出来事だった。
クリエイターEXPO出展に関してはnoteにまとめました。合計4本。びっっくりするほど長いけど、よければ暇つぶしにどうぞ…。
第14回クリエイターEXPO初出展の記録_準備編
身の回りのこととしては、友人知人と会う頻度が上がってきた。いい傾向です。知人が東京に来るタイミングで声をかけてもらったり、東京や近郊に住む友人たちと遊んだり。あと、4年ぶりに島に帰ったとき、突然連絡を取ったにも関わらず会ってくれた友人知人たちの「ゆるくばし(もてなし)」の精神が沁みました。島を離れお客さんの立場になって、改めて学ぶことが多い。
SNSやメッセージなどで互いの近況をわかったつもりでも、実際に会って受け取る情報量や空気感はまた別もの。コロナ禍に思い知らされましたが、あらためて痛感した1年でした。人に、会うぞ。
そして健康面。子の風邪をもらう頻度は格段に増えたので気をつけたい。また、日々受け続けるホルモンや気圧の影響を小さく保つための工夫が必要なので、引き続き前向きに対処できたらいいな。
ピラティスもなんとなく続いています。精神性にタッチせず、インナーの筋肉を地味に淡々と動かさ作業性が向いているようです。もう少し頻度を上げられたらいいな…。
さらに、去年の春から送迎用の電動アシスト自転車を手に入れ、車で行くほどじゃないけど距離があるエリアへ出かけるハードルがぐんと下がりました。自転車をこぐ行為も、自分の力で進んでいる実感を伴うのが楽しい。アシストされていても楽しい。行動範囲が広がるとポジティブになれますね。
それらをふまえて2025年。毎年恒例の「漢字1文字を今年のテーマとしてぼんやり掲げる」ですが
「向」
かな。
新しいことや未知の領域へ躊躇いなく向かって行きたい、自分の枠の向こう側にも行ってみたい、自身や身近な人と向き合う時間を取りたい、後ろ向きでも前向きでもアリ、趣向は凝らし続けるぞ…といったイメージです。
これを機に「向」という字について調べてみたところ、家屋北側に設けた明かり取りの窓をかたどっているそうです。実際に住宅をつくる上でも、北向き窓は、大きさや配置の工夫次第で部屋を明るくでき、湿気や風の通り道になるなど、重要な要素の一つらしい。風の通り道…という点では去年の一文字「風」ともリンクしていたので、この漢字にしてみました。果たして。
業務面における長期目標「どんなに細くなってもいいから長く」は今年も継続しつつ、たくさん遊んで仕事して人と会っておしゃべりできたら嬉しいです。
もちろん、お茶やごはんや遊びやお仕事、依頼以前のお問い合わせや雑談などのお声がけも、どしどしお待ちしています。
1人1人が、家族といても、誰かといても、1人でいても、どんな状況や環境のもとにあっても、安らぐ時間があり、心が躍ることを少しでも多く見つけられる、穏やかな1年になりますように。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします!
2024年12月30日
ムビナナ1周年ウィークと上映会ライビュの衝撃
ムビナナについては、長くなったので記事を独立させることにしました。去年もあんなに書いたのにね…。
ムビナナ、こと「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4 bit BEYOND THE PERiOD」公開1周年の再上映ウィークと、1周年記念上映会のライブビューイングへ出かけました。去年ほどではないけど、上映されていると観に行ってしまう。それがムビナナ。ドルビーを観て、用事の合間にもう1回観て、6月の上映会ライビュで度肝を抜かれた。

再上映ウィークの少し前、山本健介監督が登壇したAutodeskセミナーの、ムビナナ制作におけるデータの流れに関するお話を興味深く聴きました。
3DCGアニメーションを鑑賞する際に意識することの多い、声や身体(モーションキャプチャー)、フェイシャル(表情)などのお芝居は、実は作業のほんの入り口。
その先に待っている、「ズレた16人のフォーメーションデータを微調整する」「たくさん撮った仮想現実ライブ会場の撮影データからアングルを決める」「1人1人の表情を細かく整える」「背景や光を足す」といった工程の方がずっと長いそうなのです。
具体的なプロセスを聴きながら「あんなにムビナナに通ったのに、毎度アイドルの応援に夢中で、見えていない部分が多いんじゃないか…??」と気づく私。
なかでも、監督が何気なく話していた「これで撮ると、横からのライトの光が丸じゃなくて少し楕円に映るから」とカメラの撮影レンズ(!)まで細かく指定した話に痺れた。
とはいえアニメーションなので、実際にそのレンズを使うというよりは、そのレンズを使って撮った「画面」を作り出すことになるわけですよね…。改めて口にするのも憚られるほどの、プロフェッショナルの画面づくり。
こうした裏話を踏まえて久しぶりに浴びたムビナナは、16人の魅力を的確に捉え届けたスタッフの皆さんのお仕事に思いを馳せてしまい、余計に泣けました。エンドロール中ずっと拍手していたかったけど堪えた。
歌っているキャラに重なるから、この床置きライトをこのアングルの時は間引こうとか、人間の横顔の造形など、アニメーションの「リアルだとこうはならない表現」を成立させるところが好きなのですが、そんなアニメの魅力とリアルライブの高揚感をいっぺんに浴びたら呑み込まれるよなあ…と妙に納得。
「やっぱりムビナナ、いいよねえ」と「私はアニメーションの表現が大好きだーーー!」のふたつを再認識できた再上映ウィークでした。

再上映に合わせた映画館のポップが嬉しくて、人生初のぬい撮りをしてしまった。

ぬいぐるみを撮ることに慣れていないことが写真からも伺えますね…。
一方の「ムビナナ1周年上映会」は、幕張のイベントホールに集い、鳴り物や応援グッズを持ち込んでムビナナを観よう!という企画です。
キャスト登壇のトークショーパートもありつつ、メインはもちろん、ライブ演出付きで観るムビナナ。
ペンライトやうちわなどの応援グッズに加えて鳴り物OK!ということで,通称トンチキ上映会。私は映画館でライブビューイングを観ました。
…ライブ映画をイベントホールで…?さらにその様子をライビュ?と最初は全然飲み込めなかったけど、実際行ってみると「イベントホールで行う上映会」をライビュへと送出する仕事に感動。
スクリーンで上映されているムビナナとのズレなく、配信用音声と会場の音声を混ぜる。完パケ映像のアイドルが映るスクリーンを、角度や表情を狙って撮影する。映像内の客席と、実際のイベントホールの客席をオーバーラップさせる…という一つずつの細やかな工夫で、幕張イベントホールもライビュ会場の映画館も、レインボーアリーナになっていた。
この日のIncomplete Ruler、天さんが今まで見たことない表情をしていた気すらしたんですよ。ムビナナが映るスクリーンの切り取り方で、新たな魅力を引き出されていることに感動しました。
結局トンチキな鳴り物は用意せず、ペンライトとモンぬい持参で精一杯だったけど、十分。ライブとしても、生放送に通じるライブ送出技術としてもいい体験ができました。

扱いに慣れておらず,劇場内をコロンコロン転がった2モン。近くのマネさんが拾ってくれて嬉し恥ずかしでした…。
なんだかんだ今年も楽しかったな、ムビナナ。来年のアイドリッシュセブン10周年も今から楽しみです。
アイドリッシュセブンにゴボった経緯や、去年足繁く通ったムビナナの鑑賞記録はnoteにまとめました。
↓↓↓↓↓
アイドル16人に落っこちたムビナナを振り返る
ムビナナ、こと「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4 bit BEYOND THE PERiOD」公開1周年の再上映ウィークと、1周年記念上映会のライブビューイングへ出かけました。去年ほどではないけど、上映されていると観に行ってしまう。それがムビナナ。ドルビーを観て、用事の合間にもう1回観て、6月の上映会ライビュで度肝を抜かれた。

再上映ウィークの少し前、山本健介監督が登壇したAutodeskセミナーの、ムビナナ制作におけるデータの流れに関するお話を興味深く聴きました。
3DCGアニメーションを鑑賞する際に意識することの多い、声や身体(モーションキャプチャー)、フェイシャル(表情)などのお芝居は、実は作業のほんの入り口。
その先に待っている、「ズレた16人のフォーメーションデータを微調整する」「たくさん撮った仮想現実ライブ会場の撮影データからアングルを決める」「1人1人の表情を細かく整える」「背景や光を足す」といった工程の方がずっと長いそうなのです。
具体的なプロセスを聴きながら「あんなにムビナナに通ったのに、毎度アイドルの応援に夢中で、見えていない部分が多いんじゃないか…??」と気づく私。
なかでも、監督が何気なく話していた「これで撮ると、横からのライトの光が丸じゃなくて少し楕円に映るから」とカメラの撮影レンズ(!)まで細かく指定した話に痺れた。
とはいえアニメーションなので、実際にそのレンズを使うというよりは、そのレンズを使って撮った「画面」を作り出すことになるわけですよね…。改めて口にするのも憚られるほどの、プロフェッショナルの画面づくり。
こうした裏話を踏まえて久しぶりに浴びたムビナナは、16人の魅力を的確に捉え届けたスタッフの皆さんのお仕事に思いを馳せてしまい、余計に泣けました。エンドロール中ずっと拍手していたかったけど堪えた。
歌っているキャラに重なるから、この床置きライトをこのアングルの時は間引こうとか、人間の横顔の造形など、アニメーションの「リアルだとこうはならない表現」を成立させるところが好きなのですが、そんなアニメの魅力とリアルライブの高揚感をいっぺんに浴びたら呑み込まれるよなあ…と妙に納得。
「やっぱりムビナナ、いいよねえ」と「私はアニメーションの表現が大好きだーーー!」のふたつを再認識できた再上映ウィークでした。

再上映に合わせた映画館のポップが嬉しくて、人生初のぬい撮りをしてしまった。

ぬいぐるみを撮ることに慣れていないことが写真からも伺えますね…。
一方の「ムビナナ1周年上映会」は、幕張のイベントホールに集い、鳴り物や応援グッズを持ち込んでムビナナを観よう!という企画です。
キャスト登壇のトークショーパートもありつつ、メインはもちろん、ライブ演出付きで観るムビナナ。
ペンライトやうちわなどの応援グッズに加えて鳴り物OK!ということで,通称トンチキ上映会。私は映画館でライブビューイングを観ました。
…ライブ映画をイベントホールで…?さらにその様子をライビュ?と最初は全然飲み込めなかったけど、実際行ってみると「イベントホールで行う上映会」をライビュへと送出する仕事に感動。
スクリーンで上映されているムビナナとのズレなく、配信用音声と会場の音声を混ぜる。完パケ映像のアイドルが映るスクリーンを、角度や表情を狙って撮影する。映像内の客席と、実際のイベントホールの客席をオーバーラップさせる…という一つずつの細やかな工夫で、幕張イベントホールもライビュ会場の映画館も、レインボーアリーナになっていた。
この日のIncomplete Ruler、天さんが今まで見たことない表情をしていた気すらしたんですよ。ムビナナが映るスクリーンの切り取り方で、新たな魅力を引き出されていることに感動しました。
結局トンチキな鳴り物は用意せず、ペンライトとモンぬい持参で精一杯だったけど、十分。ライブとしても、生放送に通じるライブ送出技術としてもいい体験ができました。

扱いに慣れておらず,劇場内をコロンコロン転がった2モン。近くのマネさんが拾ってくれて嬉し恥ずかしでした…。
なんだかんだ今年も楽しかったな、ムビナナ。来年のアイドリッシュセブン10周年も今から楽しみです。
アイドリッシュセブンにゴボった経緯や、去年足繁く通ったムビナナの鑑賞記録はnoteにまとめました。
↓↓↓↓↓
アイドル16人に落っこちたムビナナを振り返る
2024年12月30日
観た映画2024_その2
年末ギリギリですが映画の鑑賞記録、後編です。
順調に長くなっていくので、お好きな部分だけお楽しみいただけますように…!!
●ルックバック

原作がweb公開された日、いろんな議論がTLを流れていった。それらを目にしないようにしながら漫画を読んで衝撃を受けたつもりだったけど、知らない人の感想や意見が頭の中にちらついてしまっていたのだなあと、この劇場版を観た後に気づきました。
京野に認められていたことを知った藤本の嬉しさ、誇らしさ、恥ずかしさ、2人ならどこにでも!という希望が、「走る」という行為に乗っかっていた。表情も見えていたけど、2人の足取りからも感情が読めた。街なかを2人で買い物に出かける様子が頭のなかを離れない。その分、2人が別の道を歩むことになるシーンの足取りの重さがつらかった。
才能があろうとなかろうと、どんなにうちのめされようと、何が起ころうと描き続ける藤本の背中を見ていると、「描け。描けないから別の、お前の方法で手を動かし続けろ」と叱咤されている気になります。
言い訳並べて逃げ回っても、調子に乗ってスカしても、自分だけは見ているもんね…。
●化け猫あんずちゃん

アニメーションと言いつつキャストが実際に演技しているらしいぞ、という噂に興味を持って観た作品。
まずキャストの芝居を実写で撮影し、映像を画像として切り出し、そこに写っているものをトレースした絵を描き、アニメーションに起こす…という、「ロトスコープ」という手法を採用しているそう。最近だと「虎に翼」のオープニングのダンスもこの手法だそうです。
声のキャストが実写の芝居もしているので、目の前のキャラクターの奥になんとなくキャストが見えてくる気がする。なかでも森山未來さんが演じるあんずちゃん37歳は、お化けだし猫だしどでかいし…と見た目も要素ひとつひとつも人間離れしているのに、原付を乗り回す動作や視線の動き、ガラケーを操作する様子などがひとつひとつ人間っぽいのです。
「人の動きをアニメに取り込む」ということで思い浮かべるのが3DCGですが、モーションアクターの動きを取り入れるそれとはまた異なる印象。見た目はアニメーションのデフォルメ感がありながらも、動きはデフォルメしすぎない、リアルな人間の所作で興味深かった。
ストーリーは子ども向け夏休み映画の雰囲気(しかも明確な救いがあるわけではない)だけど、アニメーション表現のおもしろさを感じられて好きな作品でした。
実写とアニメの比較映像はこちらです。
●劇場版すとぷり

自分ひとりじゃ選ばない作品ってこういう作品だよね。友人のすとぷりすなーに誘ってもらいました。私は6人の名前とメンバーカラーをなんとなく把握している程度です。
実在の配信者ユニットでアニメ映画を作るってどういうことかと思ったけど、なるほどこうやるのか…これは小学生たち心掴まれるかもな…夢の学園、集められた個性豊かなメンバー、少しずつまとまって最後の試練に肩を落とし、雨上がりに虹が出るエンド。
完全にファンムービーなので、りすなーが喜ぶ小ネタもたくさん仕込まれていたそうです。
飛び込んだのが応援上映回。人数は控えめながら左右10本の指についたリングライトが光る綺麗な応援を見られたのも「他ジャンルにお邪魔した」感があっていい経験でした。
●ラストマイル

アンナチュラルとMIU404と同じ世界線だよ!という宣伝文句にもしっかり踊らされる一方、鑑賞後は本筋の、ロジスティクスセンター内で起こった出来事について考えていました。
無声化に混乱するので迂闊に口に出すのを回避したいけどやっぱり口に出してしまう日本語、ロジスティクスセンター。
アンナチュラルやMIU404に出てきた面々が、持ち場が変わっても相変わらずの姿勢で、信念を持って自分の仕事をする様子を見られたのは本当に嬉しかった。ただ、彼らとデリファスメンバーとの違いは「補充される人間に脈絡がいらない」ところなのかもしれないなと感じました。
物の流れを止めないために、多くの人が何層ものセクションで働く、欠員が出たら都度補う。自分自身も生活の中で存分にその恩恵を受けています。でも、「代わりはいくらでもいる」と「人を人と思わなくていい」はイコールではないよな…と、重い気持ちで映画館を出ました。
九ちゃんが去り、陣馬さんの相方は新人の勝俣くんになったけど、そこにもストーリー上の経緯があるから視聴者はきゃっきゃするんですよね。私もしました。
全てが終わり、エレナの後は孔になったけど、そこに受け継がれるバトンのようなものは多分ない。外資企業のビジネスの考え方かと思いきや、火野さん宇野さん親子のような「ラストマイル」を担う立場の人々にも当てはまる気がしています。
余談ですが、あんなに豪華キャストが揃っていても最初から最後まで火野さん宇野さん親子だったな…。「ラストマイル」だから当然といえば当然だろうか。
あまりにも自分たちの日常と地続きで、その後訪れたブラックフライデーは通販できなかった。
自分が当該地区のそばに住んでみて初めて感じたことですが、西武蔵野署の管内ってものすごく東京から埼玉の郊外の雰囲気をまとってるんですね!車で行ける範囲にあれもこれもあるし、確かに「ありそう」でびっくりした。
●侍タイムスリッパー

テレビ時代劇が大好きな子ども時代でした。金さん、将軍、水戸黄門に三匹が斬る。ド派手な勧善懲悪だけでなく、市井の人々の明るさ、会話の軽妙さ、ダメな大人へ向けられる人情味のある目線も、よくわからないながら「大人ってこんなに優しいのかなあ」と感じて好きでした。
そんな時代劇を作ってきたプロたちの仕事ぶりや、時代劇への愛がこれでもかと詰め込まれていて味わい深い自主制作映画。きっとこの先何度も「あ、また観たい」と思うだろうな。
ストーリーを追いかけるのも、登場人物の表情を追いかけるのも楽しかったです。主演の山口馬木也さんは「麒麟がくる」「鎌倉殿の13人」などの大河ドラマにも出演されていましたね。
特に、音が印象に残っています。轟く雷鳴や殺陣など、音響を意識するシーンが多かった。なかでも、タイムスリップしてきた侍が「斬られ役」としての仕事を始め、師匠と木刀を交わす稽古場のシーン!鏡はあるし空間ひろいし床もしなるしで、道場というのは声も音も反響しやすい環境なのですが、ハウリングしそうな響きごと映像に収録されていて「そう!道場でしゃべるとこんな感じー!!」と懐かしかった。ここの音、剣道部員の各位にぜひ聴いてほしい。
そういえば道場のシーン、師匠の道着に刺繍されていた福本清三さんのお名前にグッときました。安田淳一監督とのゆかりも深い、伝説の斬られ役です。朝ドラ「カムカムエブリバディ」で松重豊さんが演じた、伴虚無蔵のモデルになった方でもあります。師匠のセリフやエンドロールなど、2021年に亡くなった福本さんへのリスペクトと感謝もさまざまなところから感じられました。
●ルート29

ロードムービーは、その「ロード」を知っていると一層楽しめるよな…もう少し道を知りたい…!と感じた。姫路市から鳥取市へと向かう国道29号線を行く、トンボ(綾瀬はるかさん)とハル(大沢一菜さん)の物語です。
横一列に並んだり棒立ちしたりした人物を正面や真横のアングルから捉えるという、平面的な構図が印象的でした。理屈でうまく説明できないけど、ふた昔くらい前に見覚えのあるシュールな雰囲気も感じた。
2人は道中、人と出会ったり去られたり一緒に歩いたりします。どの人もどこか上の空というか現実味のなさを抱えているなか、中盤に出てくるトンボの姉が、作中の人物の中でも特に異質だった。トンボの肉親という関係性もあるのか、一人平凡な現実を生きているようで、どこかほの暗くて、生きづらそうで。夜、彼女が独りごとのように、けれど一方的に妹のトンボへ言葉を投げかけるシーン、自分が責められているようで心臓がキュッとしました。本人の生きづらさも伝わってくるし、トンボへの本音もつらい。逃げ場がない。
最終的に2人は旅を終えて「現実的に」離れることになるんだけど、最後それぞれが見た景色の先に、少しでも救いがあってほしい。
以上です!長く書いてしまった!!お付き合いいただきありがとうございました。
来年は月1本以上観られるといいな。もう少しこまめにブログに書きたい気持ちもありますが、1本ずつ書く余裕があるかどうかはちょっと怪しい。さらに、年末を言い訳に今回のようにまとめて書き連ねるのも好きな作業なんですよね。ひところnoteにまとめていたアニメの鑑賞記録を思い出して、おかげさまで楽しかったです!
来年は半年か3ヶ月おきくらいにまとめられたらいいかな。ざっくりとした目標にします。
さらに、ムビナナ1周年と上映会については、さらに長くなったため次の記事に独立させます!
順調に長くなっていくので、お好きな部分だけお楽しみいただけますように…!!
●ルックバック

原作がweb公開された日、いろんな議論がTLを流れていった。それらを目にしないようにしながら漫画を読んで衝撃を受けたつもりだったけど、知らない人の感想や意見が頭の中にちらついてしまっていたのだなあと、この劇場版を観た後に気づきました。
京野に認められていたことを知った藤本の嬉しさ、誇らしさ、恥ずかしさ、2人ならどこにでも!という希望が、「走る」という行為に乗っかっていた。表情も見えていたけど、2人の足取りからも感情が読めた。街なかを2人で買い物に出かける様子が頭のなかを離れない。その分、2人が別の道を歩むことになるシーンの足取りの重さがつらかった。
才能があろうとなかろうと、どんなにうちのめされようと、何が起ころうと描き続ける藤本の背中を見ていると、「描け。描けないから別の、お前の方法で手を動かし続けろ」と叱咤されている気になります。
言い訳並べて逃げ回っても、調子に乗ってスカしても、自分だけは見ているもんね…。
●化け猫あんずちゃん

アニメーションと言いつつキャストが実際に演技しているらしいぞ、という噂に興味を持って観た作品。
まずキャストの芝居を実写で撮影し、映像を画像として切り出し、そこに写っているものをトレースした絵を描き、アニメーションに起こす…という、「ロトスコープ」という手法を採用しているそう。最近だと「虎に翼」のオープニングのダンスもこの手法だそうです。
声のキャストが実写の芝居もしているので、目の前のキャラクターの奥になんとなくキャストが見えてくる気がする。なかでも森山未來さんが演じるあんずちゃん37歳は、お化けだし猫だしどでかいし…と見た目も要素ひとつひとつも人間離れしているのに、原付を乗り回す動作や視線の動き、ガラケーを操作する様子などがひとつひとつ人間っぽいのです。
「人の動きをアニメに取り込む」ということで思い浮かべるのが3DCGですが、モーションアクターの動きを取り入れるそれとはまた異なる印象。見た目はアニメーションのデフォルメ感がありながらも、動きはデフォルメしすぎない、リアルな人間の所作で興味深かった。
ストーリーは子ども向け夏休み映画の雰囲気(しかも明確な救いがあるわけではない)だけど、アニメーション表現のおもしろさを感じられて好きな作品でした。
実写とアニメの比較映像はこちらです。
●劇場版すとぷり

自分ひとりじゃ選ばない作品ってこういう作品だよね。友人のすとぷりすなーに誘ってもらいました。私は6人の名前とメンバーカラーをなんとなく把握している程度です。
実在の配信者ユニットでアニメ映画を作るってどういうことかと思ったけど、なるほどこうやるのか…これは小学生たち心掴まれるかもな…夢の学園、集められた個性豊かなメンバー、少しずつまとまって最後の試練に肩を落とし、雨上がりに虹が出るエンド。
完全にファンムービーなので、りすなーが喜ぶ小ネタもたくさん仕込まれていたそうです。
飛び込んだのが応援上映回。人数は控えめながら左右10本の指についたリングライトが光る綺麗な応援を見られたのも「他ジャンルにお邪魔した」感があっていい経験でした。
●ラストマイル

アンナチュラルとMIU404と同じ世界線だよ!という宣伝文句にもしっかり踊らされる一方、鑑賞後は本筋の、ロジスティクスセンター内で起こった出来事について考えていました。
無声化に混乱するので迂闊に口に出すのを回避したいけどやっぱり口に出してしまう日本語、ロジスティクスセンター。
アンナチュラルやMIU404に出てきた面々が、持ち場が変わっても相変わらずの姿勢で、信念を持って自分の仕事をする様子を見られたのは本当に嬉しかった。ただ、彼らとデリファスメンバーとの違いは「補充される人間に脈絡がいらない」ところなのかもしれないなと感じました。
物の流れを止めないために、多くの人が何層ものセクションで働く、欠員が出たら都度補う。自分自身も生活の中で存分にその恩恵を受けています。でも、「代わりはいくらでもいる」と「人を人と思わなくていい」はイコールではないよな…と、重い気持ちで映画館を出ました。
九ちゃんが去り、陣馬さんの相方は新人の勝俣くんになったけど、そこにもストーリー上の経緯があるから視聴者はきゃっきゃするんですよね。私もしました。
全てが終わり、エレナの後は孔になったけど、そこに受け継がれるバトンのようなものは多分ない。外資企業のビジネスの考え方かと思いきや、火野さん宇野さん親子のような「ラストマイル」を担う立場の人々にも当てはまる気がしています。
余談ですが、あんなに豪華キャストが揃っていても最初から最後まで火野さん宇野さん親子だったな…。「ラストマイル」だから当然といえば当然だろうか。
あまりにも自分たちの日常と地続きで、その後訪れたブラックフライデーは通販できなかった。
自分が当該地区のそばに住んでみて初めて感じたことですが、西武蔵野署の管内ってものすごく東京から埼玉の郊外の雰囲気をまとってるんですね!車で行ける範囲にあれもこれもあるし、確かに「ありそう」でびっくりした。
●侍タイムスリッパー

テレビ時代劇が大好きな子ども時代でした。金さん、将軍、水戸黄門に三匹が斬る。ド派手な勧善懲悪だけでなく、市井の人々の明るさ、会話の軽妙さ、ダメな大人へ向けられる人情味のある目線も、よくわからないながら「大人ってこんなに優しいのかなあ」と感じて好きでした。
そんな時代劇を作ってきたプロたちの仕事ぶりや、時代劇への愛がこれでもかと詰め込まれていて味わい深い自主制作映画。きっとこの先何度も「あ、また観たい」と思うだろうな。
ストーリーを追いかけるのも、登場人物の表情を追いかけるのも楽しかったです。主演の山口馬木也さんは「麒麟がくる」「鎌倉殿の13人」などの大河ドラマにも出演されていましたね。
特に、音が印象に残っています。轟く雷鳴や殺陣など、音響を意識するシーンが多かった。なかでも、タイムスリップしてきた侍が「斬られ役」としての仕事を始め、師匠と木刀を交わす稽古場のシーン!鏡はあるし空間ひろいし床もしなるしで、道場というのは声も音も反響しやすい環境なのですが、ハウリングしそうな響きごと映像に収録されていて「そう!道場でしゃべるとこんな感じー!!」と懐かしかった。ここの音、剣道部員の各位にぜひ聴いてほしい。
そういえば道場のシーン、師匠の道着に刺繍されていた福本清三さんのお名前にグッときました。安田淳一監督とのゆかりも深い、伝説の斬られ役です。朝ドラ「カムカムエブリバディ」で松重豊さんが演じた、伴虚無蔵のモデルになった方でもあります。師匠のセリフやエンドロールなど、2021年に亡くなった福本さんへのリスペクトと感謝もさまざまなところから感じられました。
●ルート29

ロードムービーは、その「ロード」を知っていると一層楽しめるよな…もう少し道を知りたい…!と感じた。姫路市から鳥取市へと向かう国道29号線を行く、トンボ(綾瀬はるかさん)とハル(大沢一菜さん)の物語です。
横一列に並んだり棒立ちしたりした人物を正面や真横のアングルから捉えるという、平面的な構図が印象的でした。理屈でうまく説明できないけど、ふた昔くらい前に見覚えのあるシュールな雰囲気も感じた。
2人は道中、人と出会ったり去られたり一緒に歩いたりします。どの人もどこか上の空というか現実味のなさを抱えているなか、中盤に出てくるトンボの姉が、作中の人物の中でも特に異質だった。トンボの肉親という関係性もあるのか、一人平凡な現実を生きているようで、どこかほの暗くて、生きづらそうで。夜、彼女が独りごとのように、けれど一方的に妹のトンボへ言葉を投げかけるシーン、自分が責められているようで心臓がキュッとしました。本人の生きづらさも伝わってくるし、トンボへの本音もつらい。逃げ場がない。
最終的に2人は旅を終えて「現実的に」離れることになるんだけど、最後それぞれが見た景色の先に、少しでも救いがあってほしい。
以上です!長く書いてしまった!!お付き合いいただきありがとうございました。
来年は月1本以上観られるといいな。もう少しこまめにブログに書きたい気持ちもありますが、1本ずつ書く余裕があるかどうかはちょっと怪しい。さらに、年末を言い訳に今回のようにまとめて書き連ねるのも好きな作業なんですよね。ひところnoteにまとめていたアニメの鑑賞記録を思い出して、おかげさまで楽しかったです!
来年は半年か3ヶ月おきくらいにまとめられたらいいかな。ざっくりとした目標にします。
さらに、ムビナナ1周年と上映会については、さらに長くなったため次の記事に独立させます!
2024年12月20日
観た映画2024_その1
今年、映画館に出かけた回数は16回、そのうち2回めの作品が3本(ゴジラ、シナぷしゅ、ラストマイル)、ムビナナは3回ですが別枠(後半にまとめます)、ネトフリで観た作品が1本。観た新作としては11本でした。
今年はブログに映画の感想を書かなかったな。確認してみるとブログどころかSNSにも何も書かなかった作品もあったので、前後編に分けてざざっと振り返ります。
●ハイキュー!! IMAX

ついにシリーズ通しても大事な、因縁の対決!「ゴミ捨て場の決戦」だああああ!という喜びもそこそこに「…こんなにリッチな映像をこんなに矢継ぎ早に浴びせられていいんだろうか…」と圧倒されっぱなしだった作品です。
「ハイキュー!!」はテレビシリーズも、実際のバレー中継さながらの試合シーンが好きなんです。今何があった!?と理解できずに何度も見返してしまう。バレーボールの魅力の一つでもある、ボールに触れる一瞬で点数を得る、または失うスピード感が表現されているんですよね。大画面と大音響で試合を浴びられて幸せだったな…。ハイキュー!!の魅力が詰まっていた。今回は1試合をじっくり描く構成だったのでなおさら。
その昔、たまたまつけていたテレビで夏合宿の自主練あたりの話をやっていて、キャラクターの知識もなくぼーっと眺めたのがハイキュー!!との出会いだった。だからどうしても自主練メンバーや月島山口には感情移入してしまうし、今回も手に汗握って見守りました。
それにしたって研磨のあの顔、ゾッとしましたね…。
シリーズ通して登場するチーム数も人数も多いし、人の数だけドラマがあるので推しなんか1人に絞れないけど、飄々としたリーダーとひねくれ眼鏡キャラに惹かれる傾向があるので黒尾鉄朗さんが好きです。あとツッキー。

●ゴジラ-1.0(2回め)IMAX

2023年の年末に初めて観て、3月にIMAXでも観ました。
とにかくこのゴジラは怖い。背鰭が一つ一つ光って絶望光線を出すところがそこはかとなく恐怖を呼び起こしており大変好みです。
「橋爪功さんやっぱりいるじゃん!」と、あのシーンで声が出ました。上映開始からしばらく経ってカメオ出演が発表されましたね。やっぱりそうだったよね…。
●漫才協会 THE MOVIE 舞台の上の懲りない面々
一般社団法人漫才協会の会長となった、ナイツ塙宣之さんの監督作。
浅草・東洋館を主な舞台に、ご存知青空球児・好児師匠、テレビ番組の仲直り企画で人気が爆発したおぼん・こぼん師匠、ねづっちさん、U字工事や錦鯉などなど、協会に所属するレジェンドから若手までのインタビューを中心に進むドキュメンタリーです。
事故で腕を失い、舞台復帰に向けてリハビリを続ける大空遊平師匠が久しぶりに見せたスーツ姿、凛々しくてかっこよかった。
舞台が居場所、という芸人の皆さんのようすを、少しだけ覗かせてもらった気持ちです。
●オッペンハイマー
「原爆の父」ロバート・オッペンハイマーの生涯を描いた伝記映画。
1950年代にソ連のスパイ疑惑を受けたオッペンハイマーが追及を受ける聴聞会の様子と、オッペンハイマー自身の人生が交差しながら進んでいきます。
行ったり来たりする時系列に翻弄されながら追いかけました。
研究、実験、成功、実用化…と順調な階段を登っているように見えるけど、観ている自分はそれらのサクセスストーリーを喜べるはずもなく、ずっと苦虫を噛んでいるような感覚だった。その理由は「日本で生まれ育った私は、原爆が落とされたその先の光景を何度となく見ているから」なんだけど、映画のなかで彼自身も、投下直後の人々の姿を幻視していたのが意外で印象的でした。「優秀な科学者」とはいえ1人の人間が作った兵器で、私たちと同じ人間が暮らす街に落とされたことを自覚していたんだな、「国対国」の形をした戦争が「人対人」の殺戮だったことに、改めて気づかされます。
●シティーハンター(Netflix)

小学生低学年の頃に好きだった大人は冴羽獠、憧れの職業はレオタード怪盗3姉妹でした。
学校から帰る時間帯に再放送されていたシティーハンターとキャッツ・アイを、ハマっている自覚すらなく観て育った幼少期です。
だからこそ、2019年の劇場版アニメ「新宿プライベート・アイズ」を観た後、ブログに「私が観たかったのは、あの頃の懐古でも『今はできなくなったあの表現』でもないんだよな〜」などとダラダラぐちぐち書いてしまったのでした。
さらに今回は実写化。正直恐る恐る観ましたらば、令和の今の新宿に、あの頃の獠ちゃんと香がいた。
インティマシー・コーディネーターという専門職も入り、キャストと制作スタッフが議論を重ね、古臭くなく、下品でもなく、でも原作の軽やかさや猥雑さ、ガンアクションへのリスペクトは惜しみなく詰め込んだ世界観とキャラクター。感動しました。
確かに今なら敵襲の一発目に「ちわー!ウーバーイーツでーす!」って言いそうだもんね。
鈴木亮平さんの銃の扱いや佇まい、顎のラインまで獠ちゃんだった。森田望智さんは当たり前ですが「花江ちゃん」じゃなくて香だった。槇村の安藤政信さんも、槇村の雰囲気まんまだった。
最後に流れるゲワイまで、最高の実写化でした。
以前から鈴木亮平さんが好きな友人は、今作を機に1987年版のアニメを観始めたそうです。自分が生まれるずっと前の作品だし下ネタもあるし、時代背景の違いもあってカルチャーショックが大きかっただろうに…気合いが入っている。
そんな彼女からアニメ版の感想が聴けて嬉しかったし、その流れで「新宿プライベート・アイズ」の感想で意気投合したこともいい思い出です。
なお、公開当時ハッキリとは言えないけどモヤモヤぐるぐる書き連ねた「新宿プライベート・アイズ」の感想文はこちらです。ハッキリ言っても良かったんだろうけどね…うーん…。
https://au1982917.amamin.jp/e724445.html
ちなみに実写版といえば、フランスの実写版シティーハンター!原作と日本版アニメへの愛とリスペクトが溢れていて大好きです。難しいことから離れ、軽い気持ちで観たい時におすすめ。2021年の観た映画振り返りでも少し書いたかな。

こちらも、槇村が大変に槇村でいいんですよ……。あと、これはネタバレですが、最後は止め絵になってゲワイです。
●アンパンマン ばいきんまんと絵本のルルン

鉄拳一つで万事解決するアンパンマンにも怯まない、ばいきんまんの不屈の悪知恵とDIY精神、クリエイティビティをずっとリスペクトしている。やめない、懲りない、手を止めない。今作には、そんなばいきんまんの魅力がこれでもかと詰め込まれているのでおすすめです。詳しくは控えますが、普段持っているトンカチだけじゃなくて、カンナ削ってるんですよ。ものづくりの基本、カンナ。素晴らしい。
アンパンマンオールスターズがお好きな方には、冒頭5分がおすすめ。ナガネギマンにハンバーガーキッドなど、短い時間ながら出てくる全員にそれぞれ見せ場のあるアクションシーン、一つ一つの動作やアニメーションもリッチ!アンパンマンもイケメン!!ここだけ何度も観たかった。
…反面、ナイナイ岡村さん演じるすいとるゾウはあまりの迫力で怖かったな。明るめ、音も小さめと子どもたちに配慮したスクリーン環境で、恐怖に慄いた子どもたちの声が聞こえていました。
ひとまず半分です。
後編では7月以降の鑑賞作をまとめます。ムビナナも。
今年はブログに映画の感想を書かなかったな。確認してみるとブログどころかSNSにも何も書かなかった作品もあったので、前後編に分けてざざっと振り返ります。
●ハイキュー!! IMAX

ついにシリーズ通しても大事な、因縁の対決!「ゴミ捨て場の決戦」だああああ!という喜びもそこそこに「…こんなにリッチな映像をこんなに矢継ぎ早に浴びせられていいんだろうか…」と圧倒されっぱなしだった作品です。
「ハイキュー!!」はテレビシリーズも、実際のバレー中継さながらの試合シーンが好きなんです。今何があった!?と理解できずに何度も見返してしまう。バレーボールの魅力の一つでもある、ボールに触れる一瞬で点数を得る、または失うスピード感が表現されているんですよね。大画面と大音響で試合を浴びられて幸せだったな…。ハイキュー!!の魅力が詰まっていた。今回は1試合をじっくり描く構成だったのでなおさら。
その昔、たまたまつけていたテレビで夏合宿の自主練あたりの話をやっていて、キャラクターの知識もなくぼーっと眺めたのがハイキュー!!との出会いだった。だからどうしても自主練メンバーや月島山口には感情移入してしまうし、今回も手に汗握って見守りました。
それにしたって研磨のあの顔、ゾッとしましたね…。
シリーズ通して登場するチーム数も人数も多いし、人の数だけドラマがあるので推しなんか1人に絞れないけど、飄々としたリーダーとひねくれ眼鏡キャラに惹かれる傾向があるので黒尾鉄朗さんが好きです。あとツッキー。

●ゴジラ-1.0(2回め)IMAX

2023年の年末に初めて観て、3月にIMAXでも観ました。
とにかくこのゴジラは怖い。背鰭が一つ一つ光って絶望光線を出すところがそこはかとなく恐怖を呼び起こしており大変好みです。
「橋爪功さんやっぱりいるじゃん!」と、あのシーンで声が出ました。上映開始からしばらく経ってカメオ出演が発表されましたね。やっぱりそうだったよね…。
●漫才協会 THE MOVIE 舞台の上の懲りない面々
一般社団法人漫才協会の会長となった、ナイツ塙宣之さんの監督作。
浅草・東洋館を主な舞台に、ご存知青空球児・好児師匠、テレビ番組の仲直り企画で人気が爆発したおぼん・こぼん師匠、ねづっちさん、U字工事や錦鯉などなど、協会に所属するレジェンドから若手までのインタビューを中心に進むドキュメンタリーです。
事故で腕を失い、舞台復帰に向けてリハビリを続ける大空遊平師匠が久しぶりに見せたスーツ姿、凛々しくてかっこよかった。
舞台が居場所、という芸人の皆さんのようすを、少しだけ覗かせてもらった気持ちです。
●オッペンハイマー
「原爆の父」ロバート・オッペンハイマーの生涯を描いた伝記映画。
1950年代にソ連のスパイ疑惑を受けたオッペンハイマーが追及を受ける聴聞会の様子と、オッペンハイマー自身の人生が交差しながら進んでいきます。
行ったり来たりする時系列に翻弄されながら追いかけました。
研究、実験、成功、実用化…と順調な階段を登っているように見えるけど、観ている自分はそれらのサクセスストーリーを喜べるはずもなく、ずっと苦虫を噛んでいるような感覚だった。その理由は「日本で生まれ育った私は、原爆が落とされたその先の光景を何度となく見ているから」なんだけど、映画のなかで彼自身も、投下直後の人々の姿を幻視していたのが意外で印象的でした。「優秀な科学者」とはいえ1人の人間が作った兵器で、私たちと同じ人間が暮らす街に落とされたことを自覚していたんだな、「国対国」の形をした戦争が「人対人」の殺戮だったことに、改めて気づかされます。
●シティーハンター(Netflix)

小学生低学年の頃に好きだった大人は冴羽獠、憧れの職業はレオタード怪盗3姉妹でした。
学校から帰る時間帯に再放送されていたシティーハンターとキャッツ・アイを、ハマっている自覚すらなく観て育った幼少期です。
だからこそ、2019年の劇場版アニメ「新宿プライベート・アイズ」を観た後、ブログに「私が観たかったのは、あの頃の懐古でも『今はできなくなったあの表現』でもないんだよな〜」などとダラダラぐちぐち書いてしまったのでした。
さらに今回は実写化。正直恐る恐る観ましたらば、令和の今の新宿に、あの頃の獠ちゃんと香がいた。
インティマシー・コーディネーターという専門職も入り、キャストと制作スタッフが議論を重ね、古臭くなく、下品でもなく、でも原作の軽やかさや猥雑さ、ガンアクションへのリスペクトは惜しみなく詰め込んだ世界観とキャラクター。感動しました。
確かに今なら敵襲の一発目に「ちわー!ウーバーイーツでーす!」って言いそうだもんね。
鈴木亮平さんの銃の扱いや佇まい、顎のラインまで獠ちゃんだった。森田望智さんは当たり前ですが「花江ちゃん」じゃなくて香だった。槇村の安藤政信さんも、槇村の雰囲気まんまだった。
最後に流れるゲワイまで、最高の実写化でした。
以前から鈴木亮平さんが好きな友人は、今作を機に1987年版のアニメを観始めたそうです。自分が生まれるずっと前の作品だし下ネタもあるし、時代背景の違いもあってカルチャーショックが大きかっただろうに…気合いが入っている。
そんな彼女からアニメ版の感想が聴けて嬉しかったし、その流れで「新宿プライベート・アイズ」の感想で意気投合したこともいい思い出です。
なお、公開当時ハッキリとは言えないけどモヤモヤぐるぐる書き連ねた「新宿プライベート・アイズ」の感想文はこちらです。ハッキリ言っても良かったんだろうけどね…うーん…。
https://au1982917.amamin.jp/e724445.html
ちなみに実写版といえば、フランスの実写版シティーハンター!原作と日本版アニメへの愛とリスペクトが溢れていて大好きです。難しいことから離れ、軽い気持ちで観たい時におすすめ。2021年の観た映画振り返りでも少し書いたかな。

こちらも、槇村が大変に槇村でいいんですよ……。あと、これはネタバレですが、最後は止め絵になってゲワイです。
●アンパンマン ばいきんまんと絵本のルルン

鉄拳一つで万事解決するアンパンマンにも怯まない、ばいきんまんの不屈の悪知恵とDIY精神、クリエイティビティをずっとリスペクトしている。やめない、懲りない、手を止めない。今作には、そんなばいきんまんの魅力がこれでもかと詰め込まれているのでおすすめです。詳しくは控えますが、普段持っているトンカチだけじゃなくて、カンナ削ってるんですよ。ものづくりの基本、カンナ。素晴らしい。
アンパンマンオールスターズがお好きな方には、冒頭5分がおすすめ。ナガネギマンにハンバーガーキッドなど、短い時間ながら出てくる全員にそれぞれ見せ場のあるアクションシーン、一つ一つの動作やアニメーションもリッチ!アンパンマンもイケメン!!ここだけ何度も観たかった。
…反面、ナイナイ岡村さん演じるすいとるゾウはあまりの迫力で怖かったな。明るめ、音も小さめと子どもたちに配慮したスクリーン環境で、恐怖に慄いた子どもたちの声が聞こえていました。
ひとまず半分です。
後編では7月以降の鑑賞作をまとめます。ムビナナも。
2024年12月18日
観たライブ2024_その2
2024年ライブ鑑賞記の後編です。書き始めたら思いのほか長くなってしまいました…!
「やっぱり直後に書いておくの大事かもな…いや、時間が経った今だからこそわーわー書けるのか…?」などと余計な逡巡をしつつ、6月後半に観たビアリからどうぞ。
●Bialystocks@東京ドームシティーホール

びありすとっくす、という名前は知っている…なんかオシャレなサウンドですよね…?くらいの状態で出かけてしまい、見事に呑み込まれたビアリ。「あんなライブをするとは思わなかった」が最初の率直な印象でした。
この日は特に、音楽と照明を空間ごと味わう舞台芸術のようなコンセプトの公演。
MCも一切ないのでひたすら客席からステージを見つめる我々。拍手のタイミングもわからないままライブは進んでいくけど、そんなことも気にならない。目の前の光景を受け止めるので精一杯。
ピアノ・菊池さんの超絶技巧はライブでこそ映えますね。ライティングさえも細かく操って畳み掛けるリズムのキメ(めちゃくちゃ多い!)、緻密なサウンドを複雑に縫い合わせるようなコードボイシング、歌が終わったあとで「はじまる」アウトロの全開インプロビゼーション…もうジャズだしセッションなのよ。しかも全てが一本の映画のようにドラマティック。圧倒されてしまった。
この日は、近年すっかりビアリにハマった友人からサブスクで音源などを勧められつつ「とにかくライブを観てほしいから」と連れて行ってもらいました。確かにこれはライブハウス現地で観たい公演だし、友人知人各位に「とりあえず観て!!」と言いたくなる気持ちもわかる。音源とライブの印象がここまで違うとは思わないもんな…。
結果的に今年ビアリをもう1回観られたのですが、それはまた違うアルバムツアーで受ける印象も違った。後ほど書きます。
●東京都中学生吹奏楽コンクール@練馬文化センター

生まれる前から知っている友人の子が、我が家の近くで吹コンに出るので応援がてら聞きに出かけました。
吹奏楽経験者ながら、わたしはいわゆる吹コンには中3の夏しか縁がありません。その後に大会を見る機会もなく、自分の出場以来27年ぶりの吹コン。ひゃー!
演奏をじっくり聴くのはもちろんだけど「指揮者はあまり振り慣れていないな…『顧問だけど吹奏楽経験のない、ピアノ科卒の音楽の先生』かな」「あの指揮者の先生はシースルーブラウス、しっかり衣装だし背中のボタンも光っているな…玄人…てことは強豪…?」などという観察もいつぶりだろうか。
時間の都合で6校分しか聴けなかったのですが、それでもそれぞれのチームの特徴や「チャレンジしたいこと」が演奏から何となく伝わって興味深かった。現時点の実力と少し開きがあるかな?と思えるような難曲に挑んだとしても、想定よりテンポが早くなってトチっても、演奏している生徒の皆さんへの言葉は「ナイストライ!!おつかれさま!!!」以外ないのです。
はーーーーー懐かしかったな…。
中2の秋の大会に出られなかった事件や、個人練をしながら音楽室のベランダから眺めたグラウンドの野球部…など、芋づる式に記憶が蘇って感情が忙しかった。
個性もレベルもバラバラな1人1人が一つの曲に向き合って響かせる吹奏楽に、やっぱり今も憧れます。
●DOPING PANDA@恵比寿リキッドルーム

2022年再始動から結構時間が経ったけど、あらためて書くね。
ドーパン、再結成してくれてありがとう。
2012年の解散ライブを、私は島で、PCに映るニコ生の画面で見届けました。スターのMCや、それぞれの演奏には「もう終わり。この先は無理。再開も再集結もないよ。さようなら」という空気が満ち満ちていて、でも私はそれらを受け止めきれなくて、絶望を持て余していた。
あの日は演奏もスターの顔も、つらすぎて直視できなかった。
解散後のスターのソロ作品には、自身のコンディションや気分が都度正直に織り込まれています。当時の日本語詞、あまりに飾り気や毒気がなくて、その素直さにいつもびっくりする。
深く潜る様や前の向き方、1人での歩き方、言葉の綴り方、他のミュージシャンやバンドとの関わり方など、「フルカワユタカ」としてのスターの表現はどんどん形を変えていきました。
こうして10年間、コンディションに関わらず淡々と曲を作り、ライブをして、自身の表現を掘り下げたり他者とのセッションで磨かれてきたスターが、再びタロティ&ハヤトと合流できたことにたまらなく熱くなってしまうのです。
再結成できる関係性であったこと、スターのソロ10年を経て「新しいドーパンの作品をつくる」モチベーションが再燃していることが何よりも嬉しい。
参考までに、フルカワユタカソロ期のライブの熱苦しい感想を貼っておきます。福岡、毎回しっかりツアーに組んでくれたおかげで毎年のように観られて幸運だった。
2017年2月の福岡公演。弾き語り!
https://au1982917.amamin.jp/e640256.html
2018年3月の福岡公演。久しぶりのバンドセット!
https://au1982917.amamin.jp/e692306.html
2019年3月の福岡公演。福岡にしては皆暴れていた。
https://au1982917.amamin.jp/e726249.html
2019年はこのあと、アルバムツアーと東京ファイナルも観た。翌20年には、スターの地元山口公演も控えていたんですよね…コロナ禍め…。
語りすぎてしまった。
この日は「ドーパン1st、2ndアルバムの再現ライブ」という企画ライブではあったものの、「あの頃」に寄せに行くのではなくて今の彼らを提示してくれたことが嬉しかった。
ハヤトのタイトなドラムが、タロティーのうねうねベースが、あの頃をどんどん踏み越えてゆく。そしてドヤ顔で「アイムロックスター」と吠えるスターとギター。
「メイニア(ファンのことです)が求めるあの頃のドーパン」なんてないから、ここから3人の音楽を、また新しい表現を見せてほしい。それだけです。この先の新譜も楽しみにしています。
●Bialystocks@KT Zepp横浜

6月のドームシティホールで度肝を抜かれたビアリ、こんどはみなとみらいのZeppへ。
前回ほどの「総合芸術感」は感じないけど、やっぱりある程度全体を統制する見えない力みたいなものがはたらいていて、それはサウンドをプロデュースするキーボード・菊池さんの手によるものなんだよな。
バンドのメンバーも、ソロやアンサンブルでそれぞれがギュインギュイン伸びやかな演奏をしているのだけど、どこか統一感があるし、どんなにソロで暴れても皆しっかり「戻ってくる」んですよね。
そこに乗るボーカル・甫木元さんの繊細な歌声も良かった。
大箱のZeppでスタンディングの2-3列目、スピーカー側という近さでバンドを観察していました。
あと、やっぱり照明とのタイミング同期にこだわっている印象を受けた。ライブなんだけど映画を観ているような、視覚にもこだわっている印象。
見れば見るほど不思議な魅力を持つバンドです。
…というラインナップでした。2022年からの懸念だったフルカワユタカとドーパンを見届けられて、ひとまずよかった。
来年も少しずつ、いいライブを観たい!観られるものは観るぞ!という思いです。
「やっぱり直後に書いておくの大事かもな…いや、時間が経った今だからこそわーわー書けるのか…?」などと余計な逡巡をしつつ、6月後半に観たビアリからどうぞ。
●Bialystocks@東京ドームシティーホール

びありすとっくす、という名前は知っている…なんかオシャレなサウンドですよね…?くらいの状態で出かけてしまい、見事に呑み込まれたビアリ。「あんなライブをするとは思わなかった」が最初の率直な印象でした。
この日は特に、音楽と照明を空間ごと味わう舞台芸術のようなコンセプトの公演。
MCも一切ないのでひたすら客席からステージを見つめる我々。拍手のタイミングもわからないままライブは進んでいくけど、そんなことも気にならない。目の前の光景を受け止めるので精一杯。
ピアノ・菊池さんの超絶技巧はライブでこそ映えますね。ライティングさえも細かく操って畳み掛けるリズムのキメ(めちゃくちゃ多い!)、緻密なサウンドを複雑に縫い合わせるようなコードボイシング、歌が終わったあとで「はじまる」アウトロの全開インプロビゼーション…もうジャズだしセッションなのよ。しかも全てが一本の映画のようにドラマティック。圧倒されてしまった。
この日は、近年すっかりビアリにハマった友人からサブスクで音源などを勧められつつ「とにかくライブを観てほしいから」と連れて行ってもらいました。確かにこれはライブハウス現地で観たい公演だし、友人知人各位に「とりあえず観て!!」と言いたくなる気持ちもわかる。音源とライブの印象がここまで違うとは思わないもんな…。
結果的に今年ビアリをもう1回観られたのですが、それはまた違うアルバムツアーで受ける印象も違った。後ほど書きます。
●東京都中学生吹奏楽コンクール@練馬文化センター

生まれる前から知っている友人の子が、我が家の近くで吹コンに出るので応援がてら聞きに出かけました。
吹奏楽経験者ながら、わたしはいわゆる吹コンには中3の夏しか縁がありません。その後に大会を見る機会もなく、自分の出場以来27年ぶりの吹コン。ひゃー!
演奏をじっくり聴くのはもちろんだけど「指揮者はあまり振り慣れていないな…『顧問だけど吹奏楽経験のない、ピアノ科卒の音楽の先生』かな」「あの指揮者の先生はシースルーブラウス、しっかり衣装だし背中のボタンも光っているな…玄人…てことは強豪…?」などという観察もいつぶりだろうか。
時間の都合で6校分しか聴けなかったのですが、それでもそれぞれのチームの特徴や「チャレンジしたいこと」が演奏から何となく伝わって興味深かった。現時点の実力と少し開きがあるかな?と思えるような難曲に挑んだとしても、想定よりテンポが早くなってトチっても、演奏している生徒の皆さんへの言葉は「ナイストライ!!おつかれさま!!!」以外ないのです。
はーーーーー懐かしかったな…。
中2の秋の大会に出られなかった事件や、個人練をしながら音楽室のベランダから眺めたグラウンドの野球部…など、芋づる式に記憶が蘇って感情が忙しかった。
個性もレベルもバラバラな1人1人が一つの曲に向き合って響かせる吹奏楽に、やっぱり今も憧れます。
●DOPING PANDA@恵比寿リキッドルーム
2022年再始動から結構時間が経ったけど、あらためて書くね。
ドーパン、再結成してくれてありがとう。
2012年の解散ライブを、私は島で、PCに映るニコ生の画面で見届けました。スターのMCや、それぞれの演奏には「もう終わり。この先は無理。再開も再集結もないよ。さようなら」という空気が満ち満ちていて、でも私はそれらを受け止めきれなくて、絶望を持て余していた。
あの日は演奏もスターの顔も、つらすぎて直視できなかった。
解散後のスターのソロ作品には、自身のコンディションや気分が都度正直に織り込まれています。当時の日本語詞、あまりに飾り気や毒気がなくて、その素直さにいつもびっくりする。
深く潜る様や前の向き方、1人での歩き方、言葉の綴り方、他のミュージシャンやバンドとの関わり方など、「フルカワユタカ」としてのスターの表現はどんどん形を変えていきました。
こうして10年間、コンディションに関わらず淡々と曲を作り、ライブをして、自身の表現を掘り下げたり他者とのセッションで磨かれてきたスターが、再びタロティ&ハヤトと合流できたことにたまらなく熱くなってしまうのです。
再結成できる関係性であったこと、スターのソロ10年を経て「新しいドーパンの作品をつくる」モチベーションが再燃していることが何よりも嬉しい。
参考までに、フルカワユタカソロ期のライブの熱苦しい感想を貼っておきます。福岡、毎回しっかりツアーに組んでくれたおかげで毎年のように観られて幸運だった。
2017年2月の福岡公演。弾き語り!
https://au1982917.amamin.jp/e640256.html
2018年3月の福岡公演。久しぶりのバンドセット!
https://au1982917.amamin.jp/e692306.html
2019年3月の福岡公演。福岡にしては皆暴れていた。
https://au1982917.amamin.jp/e726249.html
2019年はこのあと、アルバムツアーと東京ファイナルも観た。翌20年には、スターの地元山口公演も控えていたんですよね…コロナ禍め…。
語りすぎてしまった。
この日は「ドーパン1st、2ndアルバムの再現ライブ」という企画ライブではあったものの、「あの頃」に寄せに行くのではなくて今の彼らを提示してくれたことが嬉しかった。
ハヤトのタイトなドラムが、タロティーのうねうねベースが、あの頃をどんどん踏み越えてゆく。そしてドヤ顔で「アイムロックスター」と吠えるスターとギター。
「メイニア(ファンのことです)が求めるあの頃のドーパン」なんてないから、ここから3人の音楽を、また新しい表現を見せてほしい。それだけです。この先の新譜も楽しみにしています。
●Bialystocks@KT Zepp横浜

6月のドームシティホールで度肝を抜かれたビアリ、こんどはみなとみらいのZeppへ。
前回ほどの「総合芸術感」は感じないけど、やっぱりある程度全体を統制する見えない力みたいなものがはたらいていて、それはサウンドをプロデュースするキーボード・菊池さんの手によるものなんだよな。
バンドのメンバーも、ソロやアンサンブルでそれぞれがギュインギュイン伸びやかな演奏をしているのだけど、どこか統一感があるし、どんなにソロで暴れても皆しっかり「戻ってくる」んですよね。
そこに乗るボーカル・甫木元さんの繊細な歌声も良かった。
大箱のZeppでスタンディングの2-3列目、スピーカー側という近さでバンドを観察していました。
あと、やっぱり照明とのタイミング同期にこだわっている印象を受けた。ライブなんだけど映画を観ているような、視覚にもこだわっている印象。
見れば見るほど不思議な魅力を持つバンドです。
…というラインナップでした。2022年からの懸念だったフルカワユタカとドーパンを見届けられて、ひとまずよかった。
来年も少しずつ、いいライブを観たい!観られるものは観るぞ!という思いです。